「恋人にラブソングを贈る」、それよりもナルシストな行為とは?
結論から言うと、
オリジナルのラブソングを、愛する人がいない場所で歌うことである。
ややこしい言い方になったのでイラスト込みで説明すると、
ライブハウスには大勢の観客がおり、その前でミュージシャンであるあなたがラブソングを歌うとする。

そのラブソングはあなたの大切な恋人に向けて書いたものであるが、
恋人は今日のライブには来ておらず、この現場に不在である。
と、こういった状況である。
そして、そんな状況にいるあなたのほうが
「君のためにラブソングを作ったんだ…
聴いて欲しい」と足を組みながら歌う者よりナルシストということである。
そんなわけはない、と思われるかもしれないが、
理屈に基づいた意見であるため仕方ないのだ。
その理屈について説明すると、
ラブソングなるものはまず、
「あなた」に対して歌うものである。
ここでいう「あなた」は恋人でも家族でも友人でも恩人でもなんでもいいのだが、
ようするに歌う相手がはっきりと決まっていると言うことだ。
それならば、「あなた」に対してのみ歌えば良いわけで、
それを「あなた」のいない場所で歌うというのは考えれば不可解だ、
というのがこの理屈である。
この時点で完全に「なるほど!確かに!」と思う方は少ないかもしれない。
しかし今一度頭を空にして考えて欲しい。
街なんかを歩いていて、
知らない兄ちゃんに話しかけられるとする。
そしていきなり
「突然ですが、あの人と出会ったのは⚪︎年前で…」から始められ、
それから、知らん兄ちゃんが好きだという、
これまた知らん姉ちゃんへの気持ちをつらつらと語られる。

散々いろんな思い出やら気持ちやら語られ、
最終的には「また◯月◯日にこの話するんで」と次回の告知をされ、
「今の話を収録したCDがあるんですけど」と営業までされる。
スピード感で言うなら通り魔や轢き逃げと同じである。
これは極端な例なので、こんなやつ実在すれば何より先に恐怖を感じるだろうが、
同時に「なら本人に言えばいいやん」と思うはずである。
それを突然、面識のない相手にべらべらと話せるのは、
ナルシスト特有の強靭メンタルがあってなせる技である。
君がいない街のライブハウスで
「君が好きだ」と歌っている
(忘れらんねえよ-この高鳴りをなんと呼ぶ)
そう、ほとんどのラブソングは本人の前で、そして一対一の場面で歌われることはない。
それに比べるなら、最初に述べたような「君のためにラブソングを作ったんだ…
聴いて欲しい」と足を組みながら歌う者は実に誠実である。
ラブソングというもの本来の役割をきちんと理解しているのである。
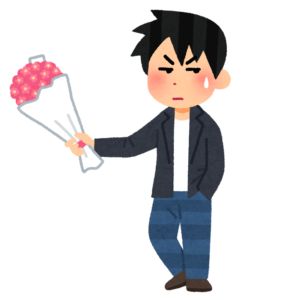
しかし、である。
得意げに屁理屈を述べた私に一つの疑問が生じた。
その者は果たして「ミュージシャン」と呼べるのだろうか?
あなたに気持ちを伝えるための手段として歌っただけでは、
ミュージシャンというニュアンスからは少しぶれる気がする。
なにより、一対一でラブソングを歌い、
もし相手が「ありがとう。とっても嬉しい!」と気持ちを受け取ってくれたなら、
その人はもう歌というものを歌う必要がなくなる。
それではやはり、ミュージシャンとは呼べないだろう。
では、「あなた」のいないところで「あなた」へ歌い続けるミュージシャンは、
何をもってしてミュージシャンというのだろうか。
それは、
いい曲を作り、いい歌を歌っていることである。
非常にざっくりした表現だが、
どんなに歌詞の内容が他人事で、
こっ恥ずかしくなったり、逆になんの感情も湧かない様なものでも、
メロディーが凄く美しいとか、歌声に独特の色気があるだとか、
トータルで魅力があればよいのである。
それこそが、面識も何もない相手にラブソングを聴かせて良い条件であり、
最低限のマナーである。
個人的なものを届ける時には最低限のラッピングが必要であり、
それもなしに押し付けをするのは、それすなわち自慰行為である。
一方、「あなた」に気持ちを伝えるべく一対一で歌う場合、
「愛を伝える」という目的がはっきりしているため、極論そこさえクリアすればクオリティはどうでもいいのである。
「うわー、下手くそ」と思うような演奏でも気持ちが伝わればオールオッケーなのだ。
そうはいかないミュージシャンだが、何より彼らにはブレイクするという目標がある。
ならば、懸命にラッピングなり皿の盛り付けなり努力したものを作り上げる必要があるのだ、
そのために、ミュージシャンは大衆の前でナルシストになる必要があったのである。
最後になるが、
あなたはラブソングを贈られたことがあるだろうか。
99%の人が「ない」と答えるだろう。
それでも、いつか贈られることがあったなら、それはとても幸せなことだ。
送った側からすればいつかは恥ずかしい思い出になるかもしれないが、
誰かと共有できる思い出は、黒歴史になんか成り得ないのである。












